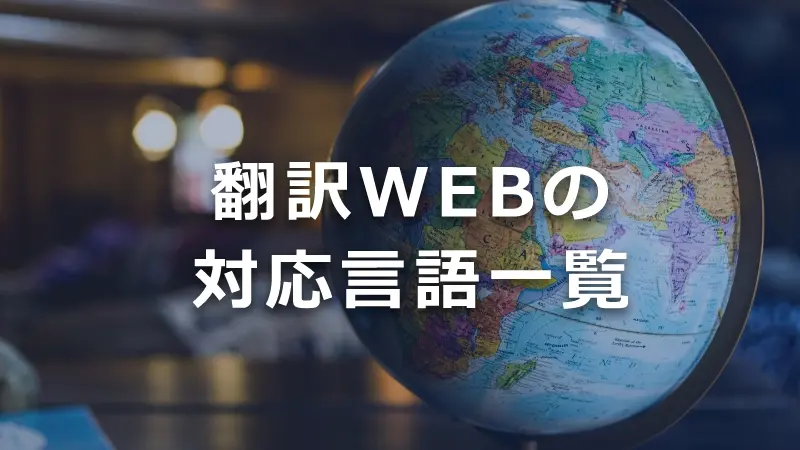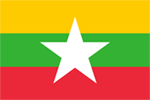
正式名称は、ミャンマー連邦共和国。かつては、ビルマの名で知られた。インドシナ半島西部に位置し、メコン地域の一角を占める。首都はネビドー。気候は、5~10月が雨季、11~2月が乾季、3~4月が暑季に当たる。面積は約68万平方km(日本の約1.8倍)、人口は約6000万人(日本の約2分の1)。約70%を占めるビルマ族をはじめ、135の民族からなる多民族国家である。言語はミャンマー語。国民の90%が仏教を信仰しており、5%がキリスト教、4%がイスラム教で続く。
ミャンマーの歴史

11世紀にパガン王朝が樹立したのち、さまざまな王朝が地域的な消長を繰り返し、1754年にコンバウン王朝によって再統一。しかし、3度の戦争の結果、1886年には英国領インドの1州としてイギリスの植民地となった。その後、太平洋戦争中の日本軍占領時期を経て、1948年にイギリスから独立するものの、クーデターによる政権掌握からビルマ式社会主義の一党独裁政治、さらに軍政が続き、2011年3月にようやく民政がスタートする。
2011年3月に23年ぶりの民政移管によって誕生したテイン・セイン大統領は、就任以来、国民民主連盟(NLD)を率いるアウン・サン・スー・チー氏と2度会談し、NLDの補欠選挙への参加を実現。さらに、10回もの恩赦によって多数の著名な政治犯を釈放するなど、民主化を積極的に推進している。
現在のミャンマー

民主化、国民和解の進展を受け、各国はミャンマーとの関係強化を図りつつある。2012年11月に、オバマ大統領が、アメリカ合衆国の大統領としては初めてミャンマーを公式訪問。1988年の民主化運動弾圧を機に冷え切っていた両国関係は、歴史的な転機を迎える。2013年5月には、テイン・セイン大統領がホワイトハウスを訪れ、オバマ大統領と会談を行った。
各国との関係正常化を踏まえ、特に2012年以降、急上昇した海外からの投資が、ミャンマーの変化をより加速させている。首都・ヤンゴンでは、モータリゼーションの本格化に伴い、交通渋滞が激しくなった。中古車の輸入は前年比40%増の12万台強に昇り、その多くは首都周辺で消費されているものだ。また、かつては1泊60~70USドルだった五つ星ホテルの宿泊代は、現在では240~250USドル。ホテルの宿泊代は、概ね4倍にまで高騰しているという。事務所の賃料も、5~7倍に上がった。
そのビジネス環境

約6300万人の人口、9割以上の識字率を誇る労働力は、日本の企業にとっては魅力的に映るだろう。実際、衣料の縫製工場をはじめとして、日系企業の進出が始まり、現地の日本人商工会議所には現在111社が登録。もっとも、現段階では、多くの企業が、駐在員事務所を開設するにとどまっている。
政情の不透明さや宗教、少数民族問題、エネルギー問題など、不安定な要素がないとはいえないが、親日で温厚な国民性や国全体を包む成長への期待感の魅力は大きい。今後、民主化の順調なプロセス、ASEANの統合を経て、東南アジアの入口としてミャンマーの経済的な位置付けはさらに高まっていくものと考えられる。
ミャンマーの工業団地
ミャンマーの工業団地は、民間工業部門の発展を後押しする目的で、1988年以降、18カ所が設けられた。工業省によると、ミャンマーには18地区の工業団地、34地区の準工業団地、7地区の新工業団地がある。
18地区の工業団地のうち、4地区24カ所の工業団地は、はヤンゴン管区にある。1990年にヤンゴン管区シュエピーター郡区に第1号工業団地が誕生したのを皮切りに、1992年にはサウス・ダゴン工業団地、1995年にはラインタヤ工業団地が設けられた。最も新しいのは、2006年設立のミャウンタカー工業団地。ヤンゴンの工業団地のほとんどは建設省住宅局によって開発されたものだが、民間企業が開発した工業団地もある。
ミンガラドン工業団地

ヤンゴン市街から北に約20km、国道に隣接し、ヤンゴン港へは約24km、ヤンゴン国際空港からはクルマで約15分という利便性の高い場所に、ヤンゴン管区への海外直接投資を目的として開発された、ミンガラドン工業団地がある。
1996年にミャンマー建設省住宅局と日本の三井物産株式会社の合弁事業としてスタートし、開業は1998年2月。約90万平方メートルの総面積に、ミャンマーの全工業団地の中でも群を抜く強固な基盤設備を持っているのが特長だ。33KVAの変圧器と配電ケーブルを備える電力、15の貯水タンクを持つ15の管井戸によって1日に5,000トンの水を供給可能な工業用水、全廃水は水処理施設に集めて2万6,215平方メートルの廃水タンクに排出する汚水処理、300のIDD回線が接続された国際通話回線などを網羅し、まさに堂々たる国際水準工業団地といえるだろう。
2006年に三井物産がJVから撤退して以降は、建設省住宅局とシンガポールの企業、ケップベンチャー社が開発を実行。工業団地の運営は、東京エンタープライズ株式会社が行っている。味の素の工場は2001年から休眠状態にあるものの、現在でも、日本、香港、シンガポール、韓国、台湾、フィリピンの企業が工場を構え、衣料を中心に電子部品、食品などを製造している。
ティラワ工業団地
ティラワ経済特別区へ


ヤンゴン市の南東約20kmに位置し、ヤンゴン管区、ヤンゴン南部地区に含まれるティラワ工業団地は、2000年に開設された。もっとも、2013年2月の段階では、食品・飲料、衣料品など、わずか3工場が稼働しているにすぎなかった。このティラワ工業団地が、今、にわかに注目を集めている。
2012年4月、テイン・セイン大統領が来日した折に、ミャンマー国家計画・経済開発大臣と日本の外務大臣および経済産業大臣との間で、ティラワ開発マスタープラン作成に関する了解覚書(MOU)を締結。さらに、2012年12月には、日本、ミャンマーの両国は、ティラワ工業団地を含む「ティラワ経済特別区」開発に関する協力覚書に署名した。
そして、2013年5月、日本、ミャンマー双方の民間企業連合によるJV設立のためのMOUを締結。2013年10月に三菱商事、丸紅、住友商事の均等出資にて設立したエム・エム・エス・ティラワ社49%、ミャンマーの官民連合51%出資によるJV設立契約書に署名するに至り、2013年11月には起工式典が開催されている。
先行開発エリア

ティラワ経済特別区の総開発面積は、東京ドーム510個分相当する約2400ha。ここに製造業の工場を中心として、商業施設や住宅、医療、教育機関などの一大集積地を形成する予定だ。
約400haの先行開発エリアに関しては、三菱商事、丸紅、住友商事の3社が、2012年夏から事業化調査と環境影響調査を共同実施。今後の工業団地の造成、販売、運営は、エム・エム・エス・ティラワ社とミャンマーの官民連合の出資で設立された、MJティラワ・デベロップメント社が行う。インフラ関連では、敷地内道路や浄水場、下水処理場、送水管、雨水・排水調整水路、配電網などの整備を計画。
造成着工に合わせ、販売も開始する方針で、縫製業や二輪・四輪の裾野産業など、100社弱と見込まれる進出企業が決まり次第、工場本体の建設も始められる。400ha規模の工業団地であれば、通常、50~100社程度の立地が見込まれるという。

2013年5月には、発電所や変電所、送電線、配電線、ガスパイプライン、港湾の整備に対し、約200億円の円借款供与が決定。先行開発エリアの周辺インフラの整備については、円借款が活用される。道路拡張、橋梁や浄水場の整備なども、円借款によって行われる可能性がある。
総事業費約170億円で2015年半ばの開業を目指し、「アジア最後のフロンティア」と呼ばれるミャンマーの大型開発が進む。
参考資料:日本貿易振興機構の資料より作成
著作権は弊社に属し、無断掲載は禁止します
お問い合わせ
各種ミャンマー語サービスについてのお問い合わせ、ご質問、お見積依頼などは、株式会社アーキ・ヴォイス 通訳翻訳事業部までご連絡ください。
またはこちらかもどうぞ。
フリーダイヤル:0120-039-289
E-mail:info@archi-voice.co.jp